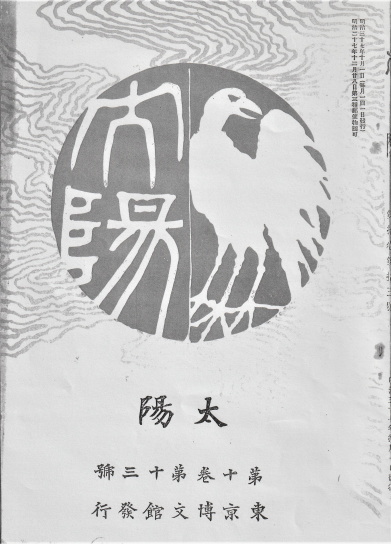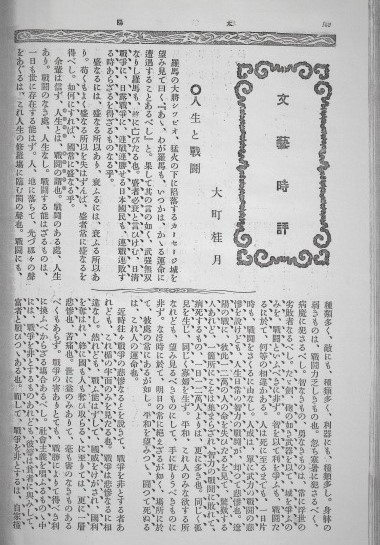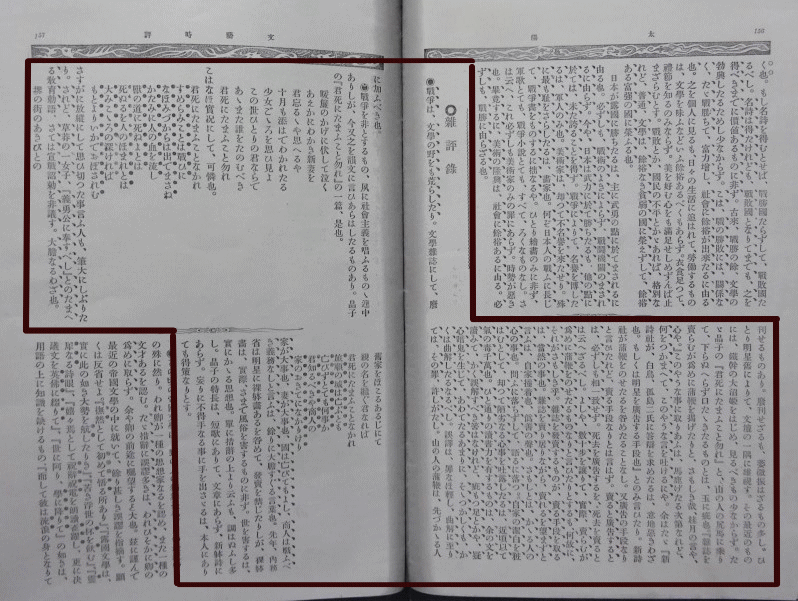2 晶子 「君死にたまふこと勿れ」を発表
|
晶子は明治33年『みだれ髪』を発表しました。
桂月の評価は『与謝野晶子女史は、日本の歌壇未曾有宇の鬼才也。その才力、むしろ鉄幹にまさる。・・(略)・・文に清少納言あり、歌に晶子女史あり、ただ女流にその其比なきのみならず、男子にもほとんど其比を見ず』と述べ、晶子の才能を讃えていましたが、その4年には文壇をまきこんだ論争がありました。
|
桂月の博文館におけるポジションは・・
桂月は、明治33年(1900年)官命で留学する友人高山樗牛(たかやま ちょぎゅう)の後任として、三顧の礼で博文館に迎えられ、初めは、『太陽』の『文芸時評』欄を担当しました。
明治35年、樗牛が病気のため亡くなると、桂月の落胆は大きく博文館退社の意を伝えたが、聞き入れてもらえる筈もなく、故樗牛の後をうけて、論壇の中枢にすわった桂月宅には、日々、新刊の著書、雑誌が大量に送り込まれてきて、様々な雑誌への時評や教育時評も執筆しました。
『批評は遂に賞揚(しょうよう)と嘲罵(ちょうば)とに帰着す』と観じた桂月は、『賞揚』よりも『嘲罵』の人であった。作家にとっても、社会にとっても『嘲罵』が『賞揚』より効ありと見ていたのです。
『桂月子がでなくては、到底文壇は賑わない』などといった記事も出て、桂月の毒舌的批判に大いに期待を寄せている傾向にありました。(高橋正著 「評伝大町桂月」より)
<参考>
高山樗牛・・・明治4年(1871年)~明治35年(1902年)。山形県鶴岡市に生まれる。伯父高山久平の養子となった。東京帝国大学で桂月と同学年。桂月は、樗牛のについて自叙伝「冷汗記」に「樗牛君は、学才もあり、世才もあり学生中より既に紳士的にして同学年中一頭地を抜き、簡単に他の追随を許さない。」とその優秀ぶりを記している。
賞揚・・ほめたたえること
嘲罵・・大声で非難すること
子・・有徳の人などへの敬称
|
① 晶子 「君死にたまふこと勿れ」 を発表
晶子は、明治37年(1904年)9月、東京新詩社の機関誌『明星』(与謝野鉄幹が主宰)誌上に『旅順の口包囲軍の中に在る弟を嘆きて』として 『君死にたまふこと勿れ』を発表しました。
~時代背景~
明治37年、日露戦争の前年で日本政府はロシアに対し宣戦を布告した。大国ロシアの韓国、満州への南進政策は日本帝国の安危に直結するものとして日本政府は戦いを宣したのだった。旅順港の戦いは一進一退を繰り返していました。
晶子は、鉄幹と結婚して二児の母となっていました。
また、実家の父は昨秋に亡くなり、弟籌三郎(ちゅうざぶろう)が三代目宗七を名乗り菓子舗駿河屋の家業を継いでいました。籌三郎は前年結婚したばかりで新妻せいは身籠っていました。
|
『君死にたまふ(う)こと勿れ』
(旅順の口包囲軍の中に在る弟を嘆きて)
ああ おとうとよ君を泣く
君死にたまふ(う)ことなかれ
末に生まれし君なれば
親のなさけはまさりしも
親は刃(やいば)をにぎらせて
人を殺せとを(お)しえしや
人を殺して死ねよとて
二十四までをそだてしや
堺の街のあきびとの
旧家をほこるあるじにて
親の名を継ぐ君なれば
君死にたまふことなかれ
旅順の城はほろぶとも
ほろびずとても何事か
君知るべきやあきびとの
家のおきてに無かりけり
君死にたもうことなかれ
すめらみことは戦いに ※すめらみこと・・今上天皇
おおみずからは出(い)でまさね ※天皇は(戦争に)自から出かけない
かたみに人の血を流し
獣(けもの)の道に死ねよとは
死ぬるを人のほまれとは ※ほまれ・・誉
大(おお)みこころの深ければ ※大御心・・天皇の心
もとよりいかで思(おぼ)されむ ※いかで・・どのように
ああ おとうとよ戦いに
君死にたもうことなかれ
すぎにし秋を父ぎみに
おくれたまえる母ぎみは
なげきの中にいたましく
わが子を召され家を守り
安(やす)しと聞ける大御代(おおみよ)も
母のしら髪(が)はまさりけく
暖簾のかげに伏して泣く
あえかにわかき新妻を ※あえか・・かよわい
君忘るるや思へるや
十月(とつき)も添はでわかれたる
少女(おとめ)ごころを思ひみよ
この世ひとりの君ならで
ああ また誰(たれ)をたのむべき
君死にたまふことなかれ
|
|
② 桂月 →晶子
この詩に対し桂月は、文壇評論家として雑誌『太陽』(博文館)に評論を掲載、主に第3節を非難をしました。
|
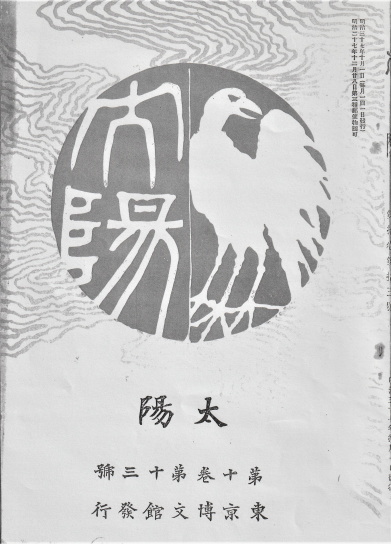 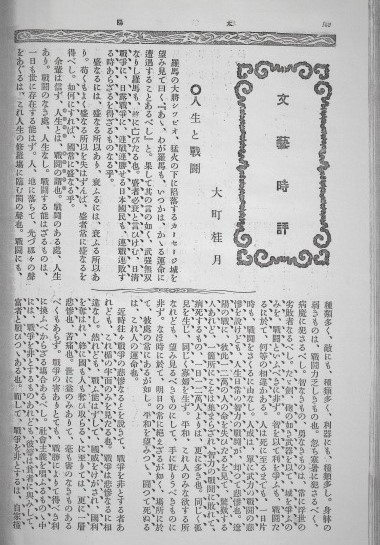
~「太陽」(実物はカラーです)昭和37年10月と、批評文が織り込まれた「文芸時評」P153↑~
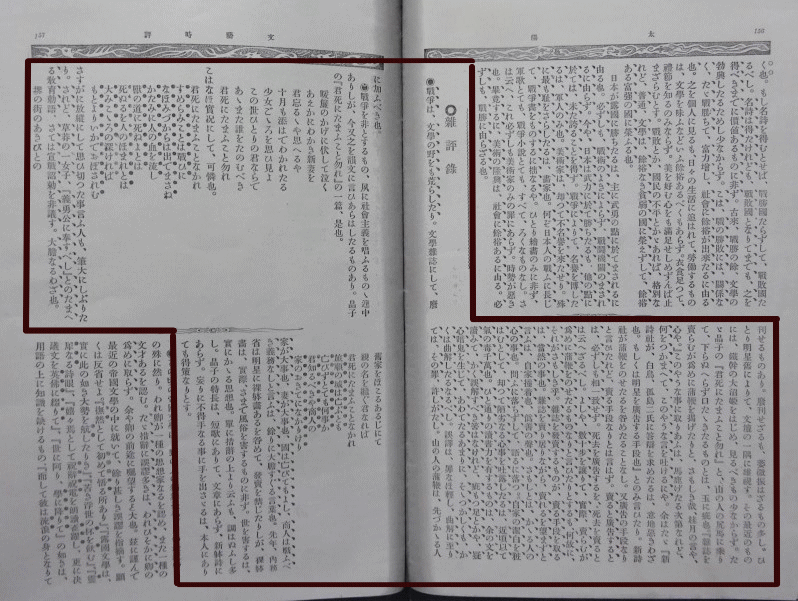
~「文芸時評」中P156~P157に「雑評録」と題したなかに見ることができます~
|
〇雑評録
(旧字体は新字体に、現代文に改めています)
◎戦争は、文学の分野をも荒らしている。文学雑誌として発刊しているものもにある。発刊できなく萎微(いび)振わないものも多い。明星だけは頑張って文壇の一隅を照らしている。その最近のものには、鉄幹の大沼姫をはじめ見るべきものが多い。
ただ晶子の『君死にたまふこと勿れ』と、人の尻馬に乗り下らぬへらず口をたたくものは、玉に疵(きず)である。『雑誌を売るために蒲鞭(ほべん)を掲げ、さもしき哉、桂月は言う、心を。』このような事に取りあうことは、馬鹿げているが何をつかまえて、このような言を吐けるのか。私はただ『新誌社が、白鳥、孤島二氏に答弁を求めたことは、意地悪いこと。いや明星を広告する手段だろうか。』と言いたい。
新誌社が蒲鞭(ほべん)をのせたことは咎(とが)めない。又広告の手段かと言いたいが、売る手段だろうとは言わない。売ると広告するとは一致しない。死去を広告することを、死去を売るとは言わないことと同じ。数十歩を譲って、実際、売るために蒲鞭(ほべん)をのせたものとしても何故に、さもしきことである。雑誌を発売するものが、売る手段を取るのは当然の事である。雑誌を売りながら、売れることを望まないと言うは自家撞着(じかどうちゃく)である。「さもし」とは、かかる人の心の事である。問うに落ちず語るに落ちる。実家の潔白を粧(よそ)い却(かえ)って卑劣な心事を吐露したことは、気の毒千万である。ひと通りの読解力を持つ者は、私の文を読んで誤解するはずはないが、疵(きず)をもつ足など疑心暗鬼を生じて、あわてるあまり曲解することもあるだろう。誤解は罪が軽い、曲解に至って罪は許(ゆる)しがたい。
◎戦争を非とするもの、前々から社会主義を唱(とな)えるもの達がいたが、今これを韻文に言いあらわしたものが晶子の『君死にたまふこと勿れ』の一篇である。
暖簾のかげに伏して泣く
あえかに若き新妻を
君忘るるや 思えるや
十月(とつき)も添わで別れたる
少女(おとめ)ごころを思いみよ
この世ひとりの君ならで
ああ また誰(たれ)を頼むべき
君死にたもうこと勿れ
これはなお実況にして、可憐也。
君死にたもうことなかれ
すめらみことは戦いに
おおみずからは出(い)でまさね
かたみに人の血を流し
獣(けもの)の道に死ねよとは
死ぬるを人の誉(ほまれ)とは
大(おお)みこころの深ければ
もとよりいかで思(おぼ)されん
さすがに放縦(ほうじゅう)で思いきった事言う人の筆は大いにしぶっている。しかし、草奔(そうもう)の一女子、『義勇(ぎゆう)公に奉(ほう)すべし』という教育勅語、さては宣戦詔勅(せんせんしょうちょく)を非難している。大胆である。
堺(さかい)の街のあきびとの
旧家を誇(ほこ)るあるじにて
親の名を継ぐ君なれば
君死にたまうことなかれ
旅順の城はほろぶとも
ほろびずとても何事(なにごと)か
君知るべきやあきびとの
家のおきてに無かりけり
家が大事也、妻が大事也、国は滅びてもよし、商人は戦うべき義務なしと言うのは、あまりにも大胆すぎる言葉である。数年前、内務省は明星に裸体書があることを咎(とが)めて発売を禁じたが、裸体書は実際それほどまで風俗を害するものではない。世を害するのは、このような思想である。単に措辞(そじ)を言うには調(ととの)わないふしが多い。晶子の特長は、短歌であって文章ではない、新体詩ではない。みだりに不得手なる事に手を出さないことは本人にも得策でる。 |
|
<参考>
萎微・・なえてしおれること
蒲鞭・・蒲(がま)の穂のむち。中国の漢時代に罪人を討つのに用い、辱めを与えるだけで痛くなかったことから寛大な政治をいう
自家撞着・・自分で自分の言行に反することをすること
問うに落ちず語るに落ちる・・人に問い詰められると用心して秘密を漏らさないが、自分から話す時に不用意に真実を話してしまう。
放縦・・規律や節度がなく、わがままなこと
あえか・・か弱く、頼りないさま
草奔・・志をもった人たちが、大きな物事を成し遂げようとすること
義勇公に奉す・・公に奉ず義勇をもって。国家や主君のためにつくす意
措辞・・言葉の使い方や辞句の配置のしかた
|
③ 晶子 →桂月
晶子は、桂月の評価を読み、驚きと怒りを禁じ得なかった。
早速、夫鉄幹宛の書簡形式で『ひらきぶみ』と題して、翌月の『明星』に一文を発表、署名は『みだれ髪』でした。
車中いて何気なく太陽を読んだところ桂月様の御評が載っていて驚きました。
・・(略)・・この御評一も二もなく服(ふく)しかねます。私が弟の手紙のはしに書きつけた歌です、あれは歌です。私が『君死にたまふこと勿れ』と歌ったこと、桂月様は大変危険な思想と仰せらですが、当節のように死ねよ、死ねよと申すこと、又何事にも忠君愛国などの文字や、おそれ多い教育勅語などを引用して論ずることは、却(かえ)って危険というものではないでしょうか。
歌は歌に候。歌よみならいから、後の人に笑われぬ、まことの心をうたわない歌に、何にねうちがあるだろうか。長い長い年月の後まで動かないまことの情け、まことの道理に私はあこがれ、心もち居ると思います。
・・(略)・・新橋渋谷などの汽車の出るところに、軍隊が立ち、見送りの親兄弟や友達親類が、行く子の手を握り、口々に『無事で帰れ、気をつけよ。』と申すこと、御眼と御耳とに必ず目がとまります。・・(略)・・このように申すことは悪いことでしょうか。私が思うに『無事で帰れ、気をつけよ、万歳』と申すことは、私のつたなき歌の『君死にたまふこと勿れ』と申すことと同じです。あれもまことの声、これもまことの声、私はまことの心をまことの声にだすより外(ほか)に、歌のよみかたを心得ません。・・(略)・・少女と申す者は誰も戦争ぎらいです。 |
<参考>
服す・・服従する
|
④ 評論家 検南 → 晶子・桂月
晶子の『ひらきぶみ』に、桂月が答える前に評論家検南が読売新聞(昭和37年11月13日)に、晶子の主張を『言い得てよし』と断じ、晶子に軍配をあげました。
同年12月にも、検南は読売新聞に、『・・顔回(がんかい)は聡明に苦しみ、文殊は知恵に煩(わずら)う、桂月子(し)は国家主義に煩(わずら)うにあらざる無きを得んや・・』と、桂月の晶子批判の根底には国家主義への偏執があると批判しました。
<参考>
顔回・・孔子の弟子、後世の儒教では四聖人として崇敬される
子・・男子の敬称
検南・・又は、角田浩々歌客(かくた こうこうかきゃく)、本名は角田謹一郎。
明治2年(1869)ー大正5年(1916) 明治の詩人、文芸評論、新聞記者、大阪の文壇で重きを成して世論形成に大きな力を持った。新聞社ごとに号を使い分け『検南』は読売新聞でつかっていました。
|
⑤ 桂月 → 晶子・検南
桂月は同年12月、翌年1月『太陽』に反論しています。
現代文で紹介します。
| 詩は情をありのままに歌えばよい。みだりに理を以(もっ)て批判すべきものではない。詩は、情をありのままに歌うべきことは、言うまでもない。しかし、情には、公情もあれば私情もあり、風俗を壊乱(かいらん)する情もあれば、社会の秩序を破壊する情もある。人が出征するに臨み、無事に帰れというだけならば普通の人情である。私が批判したのは、作者の反省を促したものであり、必ずしもふねく追求する意志はない。(12月) |
(略)・・挙国一致、旅順口の陥落を翹望(ぎょうぼう)するに当り、旅順出征の人に向かいて、旅順落ちようが落ちまいが、どうでもなし。旅順を落すは、商家の法に非ずというは奇矯(ききょう)に過ぎて、国家を嘲(あざけ)るも、また甚だしい、また弟を懐(おも)うに縁の遠い天皇を引き出し、大御心(おおみこころ)の深ければ国民に戦死せよとは宣給(たま)わじと言うに至っては反語的、もしくは婉曲(えんきょく)的、もしくは婉曲的な言い方と判断する他ない。
晶子の詩との関係を離れて言えば、私は、平生、国家主義を唱えるものである。最近、西洋では、正しく日本人を理解ようとしていて、日露戦争に連戦連勝する理由を求めて、之を武士道に帰するとしていることは、的を得たものである。しかし、武士道の最奥には皇室があることを知るべきである。万世一系の皇室は日本国民の道徳の源泉である。日本国民を団結させる楔子(けっし)である。日本の国家を維持する柱礎(ちゅうそ)である。・・(略)・・詩人に向かって、必ずしも皇室を謳歌せよとはすすめないが、皇室が教化の淵源(えんげん)であることは、日本国民として理解するできである。毒舌は詩ではない。皇室に対して毒舌を吐くことも。・・(略)・・
私が、皇室中心主義の眼をもって、晶子の詩を検すれば、乱心なり、賊子(ぞくし)なり、国家の刑罰を加うべき罪人なりと絶叫せざるを得ない。(1月) |
<参考>
ふねく・・しつこく
翹望・・強く望み待つこと
婉曲・・遠まわしに言うさま
淵源・・根本
楔子・・くさび
賊子・・親不孝な子、主君などに反逆する者
|
⑥ 晶子と桂月 話し合い~高橋正氏著『評伝 大町桂月』より~
新詩社(晶子)側は、晶子の夫鉄幹と、弁護士で明星派の論客平出修の二人で直接桂月と対決して、理非・曲直を明らかにしようと図った。この話し合いは38年1月8日、桂月は一人、居宅蜀紅園で1時間半にわたって行われました。
その経緯は『明星』2月号に掲載され、内容は新詩社側に偏った記事でした。
現代文で紹介します。
問) あなたの俗語訳を吾々が見ると故意に悪解したようである。あの歌を次のように理解できないだろうか。
天皇陛下は九重の深きにおはしまして親しく戦争の光景をご覧給わぬ、それは、もとより慈仁の御心深き陛下におかれては将卒の死について人生至極の惨事ぞと御悲嘆遊ばさぬ筈はあるまい。必ずや大御心の内は、泣いておられるだろうが、陛下ですらこの戦争を制止し給うことが難しく、やむを得ず陛下の赤子を戦場に立たしめ給うとは、なんという悲しきあさましき今の世のありさまだろうか。
答) それは、そのように理解することもできる。
問) そのように理解できるのであれば、あの歌は必ずしも危険の分子を含むは言えないのではないだろうか。如何か。
答) それだけの感情を普通に言うのであれば非難はしない。挙国一致の今日、宣戦の詔勅(しょうちょく)に対して畏れ多い。また君達の解のようであれば、水を冷たいと言うのと同じく、解りきったことを歌にしたもので何等妙なし。 |
形態は新詩社側が一方的に押し気味であった。
文中、新詩社側が提示した第三連の解釈が正解であり、昌子の真意だとすると、この詩は冴えのない平凡なものになってしまう。桂月の言うように『水を冷たいと言うのと同じく、解りきったことを歌にしたもので何等の妙なし』ということになる。晶子の真意は果たしてその程度のものであったろうか。
※妙・・不思議
|
⑦ 桂月その後
桂月は、明治38年発行の『 わが筆 』の「明治38年の1月」の項に、その心境が綴られています。
・・・旧字体は新字体に改め、現代文にて紹介します・・・
明治38年の1月は、私にとって最も苦痛の月だった。この一月(ひとつき)はほとんど酒ばかり飲んで過ごす。外形上は、ただのんきにして、楽しそうに見えただろうが、それも新年を賀して久しぶりに逢う人々のお相手をした時までだった。私に文償多く、読むべき書物も多いので、新年早々より、おおいに勉強するつもりだったが、事と志と違い、一事ならない。慚愧(ざんき)する。ままならぬが人生の常とは言いながら、私の意思はあまりに弱い。酒にあてられているなか、突然、従兄病死の知らせを受ける。雪の降る日だった。病に伏していたが、それほど重い病ではなかった。お手伝いさんが、鼻歌を歌いながら便所に行ったのを聞いているが、誰も死に際に間に合わなかった。三尺の雪に二升の血を吐いて息絶えたとの事だった。昨日まで共に碁をうつ仲だったので、悲しみにくれて、我が明治38年の1月は終わった。
※ 慚愧・・自分の見苦しさや過ちを反省して心に深く恥じること |
~資料提供は、古谷義昭氏~
|
<まとめ>
この論争を、桂月研究家高橋正氏は『評伝 大町桂月』に次のように著しています。
| 桂月の晶子詩攻撃の核心的部分は、晶子の詩が第三連を中心に天皇を怨嗟(えんさ)、非難していると解釈して、天皇絶対主義の立場からそこに攻撃の矢玉を集中している点である。晶子の詩がいわゆる反戦詩、厭戦(えんせん)詩であるという一点だけで桂月は反復攻撃した訳ではない。日露戦下に発表された反戦歌は木下尚江の『戦争の歌』(明治37年6月)、中里介山の『乱調激韵』(明治37年8月)、小杉未醒の『陣中詩篇』(明治37年11月)、大塚甲山の『砦の百合』(明治38年2月)など少なくない。桂月はこれらのすべてを黙過し、なんらの評論も加えていない。桂月が晶子詩を敢えて標的にしたのは、この詩が単なる反戦詩でなく、天皇への批判、怨嗟の感情を含んでいると解したからである。桂月は晶子詩の第三連の『すめらみことは戦ひに/おほみずからは出でませぬ』以下の条を『天皇親らは、危き戦場には臨み給わずして宮中に安座して居り給いながら、死ぬるが名誉なりとおだてて、人の子を驅(か)りて、人の血を流さしめ、獣の道に陥らしめ給う。残虐無慈悲なる御心根哉』と俗語訳した上、これは天皇に対する反語的怨嗟、毒舌であるとして、晶子を『乱心』『賊子』『罪人』なりと罵ったのである。つまり、桂月は文学作品、芸術作品を批評するのに特定のイデオロギーや恣意的なモラリズムを以って律するという、文芸評論家としてはあるまじき重大な過誤を冒したのである。・・(略)・・桂月は、詩人一般社会の『縄墨』『道徳』で律してはならないと物わかりの良いところを見せている。しかし、この『縄墨』『道徳』も国家や天皇が絡んでくると桂月の考えは大きく後退する。 |
また、桂月の孫で故大町芳章氏は『余材庵余滴 三』に次のように記しています。
桂月は当初、『余の意、もと作者の反省を足れりとす。必ずしもふねく追求するの意なし。』としたが、この論争は、第三者が介入し、文壇をまき込んだ論争に発展し、桂月も引くに引けなくなってしまったものと思っている。
桂月は、『詩人はもと情の人也。情の人たるが故に、詩あり。従って多少社会普通の縄墨(じょうぼく)をもって之を律すべからざるものあり、道徳の基準は之を宗教家、教育者に求むべし、詩人に求むべからず』と書き残しており、心のなかにはこの考えが根底にあったと思うが、多面、桂月が持っていた「忠君愛国思想」「皇室中心思想」に触れ、受け入れがたいものとなり、特に第三連は天皇を中傷誹謗したものとして我慢できなかったのではないだろうか。
桂月の書に、明治天皇の御製を書いたものがあるが、桂月とは署名せず、本名である「芳衛」と書いている。桂月としては「臣 芳衛」と署名したい気持ちを持っていたのではなかったか。
この論争のため、桂月は文芸評論家としては、特定のイデオロギーに偏りすぎるとの評価を得てしまった事件であった。 |
<参考>
ふねく・・執念深く、しつこく
縄墨・・さだめ、規則 |