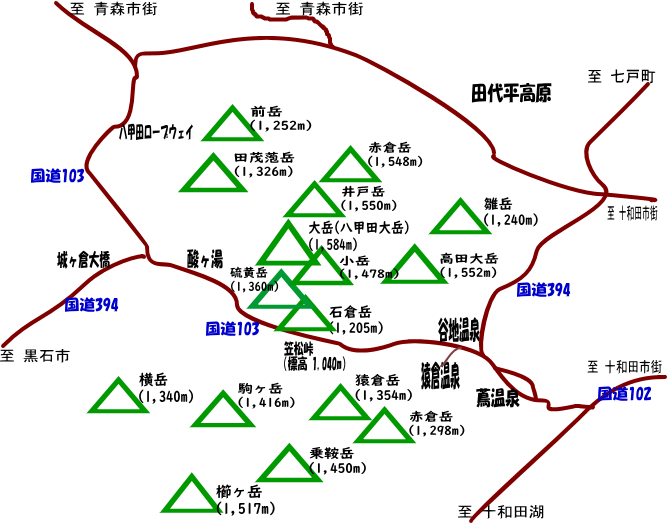八甲田 夏 |
桂月が、何度も登山している大岳(標高1,584m)夏の景色です。
|

「八甲田山神社」の鳥居をくぐって出発です ⇒
|

|

途中青森県の最高峰岩木山が見えました ⇒
|

「 地獄湯の沢 」(下記の解説看板がありました)
『この沢は、硫化水素ガスや炭酸ガスなどを噴出しています。このような硫気ガスのため岩は変質しくずれやすい地形となっています。また、普通の植物は生息できず、硫化ガスに強い植物だけが生えています。』
|

登山道の両側は、はい松です ⇒ |

大岳山頂です |
「 山に登り偃松(はいまつ)を見れば、初めて高山に登った心地がする。偃松帯の上のお花畑を見れば天上の神苑に入った心地がする。関東地方では、7・8千尺以上の山でなければ偃松はなく、お花畑もないが奥羽地方では、4・5千尺の山でこれを見ることができる。緯度の関係上、奥羽の4・5千尺は関東の7・8千尺に相当するのだ。
陸奥の八甲田山は海抜5千2百30尺で偃松帯があり、お花畑が多く、高山植物が豊富でその種類は千種類をこえる。・・・」( 桂月の紀行文「花の八甲田山」より、現代文にて)
|

夏の毛無岱です ⇒
|

大岳と一面に咲く キンコウカ
|
桂月は、大正11年8月20日は曇りでしたが、酸ヶ湯を出発して大岳登山で歌も詠んでいます。
雲の日の親しきお花畑かな 桂月
鶯(うぐいす)もきこえてお花畑かな 桂月
駒草に一杯雲に眠りけり 桂月
お花畑雲に取られて一人かな 桂月
お花畑雲にかくれるあらわれる 桂月
谷青葉蔽(おお)いきれぬ空を雲走る 桂月
私も多くの花に出会いました。ご覧ください。
|

イオウハナゴケ(地獄湯の沢)
|

マルバシモツケ
|

チングルマ
|

ミヤマキンバイ
|

ウサギギク
|

ミヤマシャクナゲ
|

ワタスゲ
|

イワオトギリ
|

キンコウカ |

キクザキイチゲ
|

ヨツバシオガマ
|

コバイケイソウ
|

ツマトリソウ |

マイヅルソウ |

アオノツガザクラ |
|