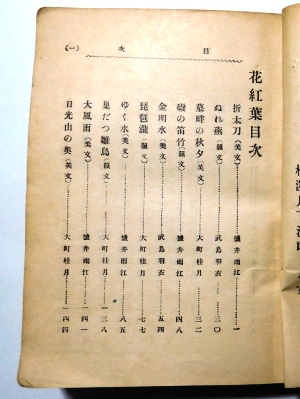|
3-2 「 墓畔の秋夕 」 (美文) ~桂月~
~苦学のなかで世話になった長兄惣作との別れを綴った「墓畔の秋夕」を紹介します~ |
|
心づくしの秋の夕べ、何とのう涙のこぼるるに、亡き兄のこと思い出(いで)て、青山なるその墳墓にもうでぬ。
さればとて布団も着せられぬ石の面、雨に風に幾多の星霜をけみしつくして、はや苔さえ生いたるに、生前好まれし花とて、われは両三枝の菊を筒にそなえて、うやうやしくぬかづくに、ありしことども、そぞろに思い出され、涙秋風に堕(お)ちておのづから声あるを覚えず。
あわれ同じき墳塋(ふんえい)累々して、香烟(こうえん)絶えてはまたつづき、西に沈みたる夕陽、一帯の暮雲に残照をとどめて、卒塔婆(そとば)の文字なお明らかに、刀稜(とうりょう)に似たる冷風肌にしみて、人を招く尾花の下に、餌をあさる狐の声のいと冷やかなるに、年まだ若き女の、丸髷(まるまげ)に結いたる髪もみだれ、袖に千行の涙を湛えて新しき墓標の下に跪(ひざまづ)くは、もろこしのいくさに夫を失いたる寡婦(かふ)にあらん。霜を戴ける老人の珠数つまぐりて卒塔婆の前に拝むは、その子の菩提を弔わんとにや。見るもの聞くもの、一として断腸の種にあらざるはなく、ものすごくもまたいたましくも、そぞろに人をして無常の感に堪えざらしむ。
げに薤上(かいじょう)の朝露かわき易くして、黄公の酒壚(しゅろ)永く 愁(うれい)を添え、鳥邊山の烟(けむり)常に絶えずして、北邙山(ほくぼうざん)上、唯々松柏(しょうはく)の声を聞く。あわれ、人生は夢か幻か、一犁(いちれい)の春雨に油々(ゆうゆう)として萌芽し、一陣の秋風に蕭々(しょうしょう)として搖落(ようらく)す。非情の草木だに、天地消長(しょうちょう)の気運を免(まぬが)るること能(あた)わず。紅顔よく幾時ぞ、黄梁一炊(こうりょういっすい)、夢は忽ち邯鄲(かんたん)の枕に破れ、栄華一瞥(いちべつ)、魂はむなしく黄壚(おうろ)の山に迷う。悼むべし、天地の形を委(い)すること未だ久しからざるに、天地の和早く己に破れぬ。
墓碑の大小は以って功徳の大小を表するに足らず、髑髏(どくろ)またいかでか○醜を弁ぜん。已(い)んぬるかな、我兄の世を去りしは昨日の如く覚ゆるに、数うれば、はや幾多の年月を経ぬ。余、碌々(ろくろく)として得る所なし。われ実に泉下の魂につぐるの言葉なきを恥づるなり。 |
<参考> 青色文字について
けみし =閲し、よく見る、年月が経過する
墳塋・・墓場
累々・・一面に重なりあって沢山あるさま
香烟・・・烟=煙・線香の煙
尾花・・ススキ
もろこし・・日本から中国をよんだ名
つまぐり =爪操る →珠数つまぐり・・数珠の玉を指であやつって
黄公の酒壚・・黄おやじの酒場
北邙山・・ 中国にある山で、王候の墓地として有名
松柏・・常緑樹は一年中葉の色が変わらないことから、節を守って変えないことのたとえ
犁・・すき・りゅう
油々・・油がひかるように、つやつやしているさま
蕭々・・ものさびしいさま
搖落・・揺れ動いて落ちること
消長・・ =盛衰
一瞥・・一見、一目
委する・・まかせる
已んぬるかな・・今となっては、どうしようもない
薤上の朝露晞(かわ)き易く
韮(にら)の上におりた朝露はかわき易く落ちやすいことから、人の命のはかなさのたとえ
黄梁一炊の夢
黄梁はきびのこと、きびが炊ける間に見た夢はつかの間の夢。栄枯盛衰もほんのひと時の夢ように、はかないものである。
邯鄲の枕
青年が邯鄲で翁から枕を借りて眠ったところ、富貴を極めた50余年の夢をみたが目覚めてみると炊きかけの黄梁もまだまだ炊きあがっていないわずかな時間であったという古事から、人生の栄枯盛衰ははかないことのたとえ。 |
|
|
愛別離苦(あいべつりく)は世の常なり。百歳いかでか百歳の人あらん。されど、余が殊(こと)に亡き兄の為に悲しむものは、貧賤無苦の中に人となり、未だ志を得ずして轗軻拓落(かんかたくらく)の間に夭折(ようせつ)したればなり。兄の半生、余は説かんと欲して、筆を投ぜしもの幾回なるを知らず。あわれ、兄のいとけなき時は家道未だ衰えざりしが、その学に志す時にいたりて始めて衰えたり。さるに兄の心中欝勃(うつぼつ)として禁ずる能わざるものあり。遂に桑梓(そうし)の地を辞して都門にのぼりたれども、学資なければ思うままに学問にいそしむこと能わず。常にこれを憾(うら)みとせり。既にして自分から餬口(ここう)の資を得ざるべからざるにいたり、蒲柳(ほりゅう)の質を以て雪を北海のほとりに踏み、未熟の学を以って帷(とばり)を南海の浜にくだし、俗事身をまとうて、また勉学するに由(よし)なく、年齢ますます加わりて二豎(しゅ)漸(ようや)く勢を逞(たくま)しうせんとす。是に於いて余に属するに、その志を継ぐべきを以てし、余に勧(すす)むるに高等の学科を修むるを以てし、資を給し、教えを垂れ、家道の艱難(かんなん)はつゆ余をして知らしめざりき。その意何ぞ慇懃(いんぎん)にして痛切なる。嗚呼(ああ)われは実に謝す、感泣(かんきゅう)のあまり、奮然(ふんぜん)として起(た)ち、孜々(しし)として勉(つと)め、不肖の身を以て自から千戴を期するの意を生ずるに至りたるもの、皆これ亡兄の賜物たらずんばあらず。兄まず余に第一高等中学に入らんことを勧めておかざりしを以て、余は自から惴(おそ)れず、これに従うて其の入学試験をうけぬ。時に兄病にかかり、帰りて故郷にありき。しきりに書を寄せて曰く、われ日に汝の成業(せいぎょう)を楽しみ、幾(ほと)んど病の身にあるを覚えず、試験の成績分らば、速(すみやか)に報道せよと。
さるに、余は終(つい)に落第せり。余の兄に背(そむ)くこと多し。兄もし不合格の報に接せば、或いは落胆して其病一層の重きを加うるならんと心をいためたれど、止むを得ず、筆とりてありのままに落第の由を告げしに、兄返事を贈って曰く、汝学に就くの日なお浅く且つ師なくして独学す。その落第せしは実に余の罪なり、汝の罪にあらず。前途なお遠し、決して一敗に懲(こり)るることなかれと。現実に余の意想外に出(い)でたれば、余は合格するよりもなお嬉しき思いをなしぬ。 |
<参考> 青色文字について
愛別離苦・・親愛な者と別れるつらさ
轗軻拓落・・志を得ないで不遇であるさま
いとけない =稚い・幼い
欝勃・・意気が盛んにわきおこるさま
桑梓・・ふるさと
夭折・・若死に
餬口・・かゆを口にするの意から、細々と暮らしをたてること
蒲柳の質・・体が弱く病気にかかりやすい体質
豎・・子ども
艱難・・災難や困難
慇懃・・礼儀正しいこと
感泣・・感激のあまり泣くこと
孜々・・熱心に励むさま
賜物たらずんばあらず・・賜物である
成業・・(学業)を成し遂げる |
|
|
後二箇月を経てまた入学試験ありたれば、余はこれを兄に報じ、且
(か)つその病を問えば、汝唯々心を潜(ひそ)めて試験の準備をなせ。病はかわりたることなければ、敢(あ)えて憂うる要せずと答えぬ。既(すで)にして余はまた試験を受けしが、其及第未だ判ぜざりしほど、忽(たちま)ち兄が帰郷の報に接せり。余は以爲(おも)えらく、兄の病癒えたるならんと。往(ゆ)いて之を新橋に迎う。時に夜雨蕭々(しょうしょう)たり。之を久うして最終の列車着きぬ。車を下(お)りるもの頗(すこぶ)る多けれども、未だ兄を見ず。怪(あや)しんで待つほどに、最も後(おく)れて出(い)づるものあり。骨立ち、髪乱れ、気息(きそく)奄々(えんえん)として歩行に堪えざるものゝ如し。近づいて之を見れば、やがて兄なりけり。
嗚呼(ああ)兄の病果して変りたることなかりしか。愚にして悟らず、臍(ほぞ)を噛むもまた及ぶべからざるなり。拝揖(はいゆう)未だ終わらざるに、兄まづ試験は如何にと問う、声さえいと苦しげなり。未だわからざれども、出来悪(あ)しかりきと云えば、憮然としてまた問わざりき。嗚呼罪の上に罪を重ね、何を以てか兄の病を慰めん。跼天蹐地(きょくてんせきち)、余幾(ほと)んど身を措(お)く処をしらざりき。この夜車を同じうして帰る途上徐(おもむ)ろに余に告げて曰く、蒼々たる鏡川の水、皎々(きょうきょう)たる桂浜の月、風景美ならざるにあらざるも、故郷の親しむべき所以(ゆえん)は、其山水にあらずして其人にあり。今や骨肉離散し親族疎隔(そかく)し、竹馬の友、或いは死し、或いは他郷に去りて、また共に談ずべきものなく、もと親しかりし人も我が零落(れいらく)を侮(あなど)りて、来り訪(と)うものとてはなし。されば故郷というは名のみにて、満目(まんもく)の生面(せいめん)、余は反(かえ)って他郷の思をなせり。寧(むし)ろ骨を真の他郷にほおむるも、親しき人々にいま一度遭(お)うて死ぬるを得ば、憾(うら)む所なしと思いたちて、医師の止(と)むるをも顧みず、病を力めて、出(い)づるなりと、言々(げんげん)痛切ならざるはなく、感極まって慰めんと欲するに辞(ことば)なく、余は唯々涙を呑めり。寓居(ぐうきょ)に着きし頃は、夜いよいよ更けぬ。雨いよいよいみじく降りぬ。往(ゆ)いて一医の門を叩けば、病と称して来らず。去りて他にゆく、また来らず。此の如きもの三回、漸く一医を迎えて診察を乞いぬ。その去るに臨み、ひそかに問えば、最早(もはや)治すべき見込なしという。嗚呼兄の病遂に医(い)すべからざるか。国手(こくしゅ)匙を投げたる後、幸にして一生を得たる人なきにあらざるを聞く。米びつしばしば空しくは我が憂うる所にあらざるなり。弊衣(へいい)寒を蔽(おお)わざるも我が厭(いと)う所にあらざるなり。唯々兄の死に瀕(ひん)して満足なる療養を尽すこと能(あた)わず。吾れ是に於て始めて、赤貧の苦しさを知れり。
兄の病は、日に重(おも)るのみ。而(しこう)して其苦痛は減ずるものの如く、死の観念もまた其脳底(のうてい)を去りたるものの如し。誤って水気を認めて肉の肥えたるものとなし、腕を撫(ぶ)して曰く、嗚呼我れあやまてり。我の病もと虚弱なるにもとづくといえども、痛飲またその一因たらずんばあらず、病癒(い)ゆの日は酒は決して飲まざるべし。われまた晏起(あんき)の癖あり。病癒(い)ゆるの日はかならず早起して適宜に運動せんと。かくて数日過ごしぬ。試験の成績は遂にわかれり。余は幸にも及第せり。之を兄に告ぐれば、莞爾(かんじ)として微笑せり。嗚呼これ実に兄が此世に於てなせる最後の笑いにてありしなり。既にして曰く、学資定めて多きを要せん。汝如何にして、これを弁(べん)ぜんとする乎(か)と。嗚呼これ兄が此世に於てなせる最後の心配にてありしなり。最後の笑いを催さしむ是なるか。最後の心配を起さしむる。非(ひ)なるか。嗚呼、余竟(きょう)に出づる所を知らず。 |
<参考> 青色文字について
既にして・・そうこうしているうちに
忽ち・・・急に
以爲えらく・・思っていることは
気息・・呼吸
奄々・・今にも息が絶えそうなさま
臍を噛む・・どうにもならないことを悔むこと
拝揖・・神道における敬礼動作の名称で会釈にあたる
跼天蹐地・・・ひどくつつしみ恐れること
鏡川・・高知市内を流れる川
皎々・・・ひかり輝くさま
零落・・落ちぶれること
侮る・・相手を見さげて軽んずること
満目・・あたり一面
生面・・初対面
言々・・ひとことひとこと
寓居・・住まい
医す・・病をなおす
国手・・医師を敬っていうことば
弊衣・・破れてぼろぼろになった衣服
厭う・・嫌がる
而して・・そうして
晏起・・朝遅く起きる
莞爾・・にっこりと笑うさま
弁ずる・・物事を処理する
非なる・・その本質は全く異なる
竟・・最後 |
|
|
夜に入りて兄遂に人事を弁ぜず。唯々昏々として眠るのみ。悲しいかな星寝室に落ち、月東壁に食(しょく)す。天は明けぬ。日は出(い)でぬ。而(しこう)して兄遂に起つ能(あた)わず。嗚呼酒はまた劉怜(りゅうれい)が墓上に到らざるべし。兄其(そ)れ何(い)づれの処にか早起きせんとする。余や幼(おさなき)にして父を失い、唯々兄に是れ依(たよ)れり。而(しこう)して兄も亦逝く。隻影(せきえい)煢々(けいけい)たり、鸇(はやぶさ)鴿(いえばと)原上われ独り飛ぶに堪えるんや。嗚呼(ああ)兄の一生は実に惨澹(さんたん)たる境遇のみなりしなり。兄の心事(しんじ)を知る者、世それ幾人かある。公叔は去りぬ、公租も逝きぬ。兄その生前の遺躅を攀(よ)ずる能(あた)わずして、空しく、その身の零丁(れいてい)を趁(お)う。巧業の世に伝えるものなく、手澤(しゅたく)の家に存するものなし。唯々知己の真情に依りて、漸く葬式は終われり。隻友(そうゆう)の厚誼(こうぎ)に依りて、漸く一基の石塔は立てり。皇城(こうじょう)の外、青山の地、風雲為に弔い、陰鬼夜哭(こく)す。
嗚呼、兄実に余につくせり。而(しこう)して余は未(いま)だ兄につくす能(あた)わず。兄たとえ自から悲しまざるも、余は実に兄のために悲しまざるを得ざるなり。顧みれば余亦幼(おさなき)にして流寓(りゅうぐう)し、或いは塾僕となり、或いは食客となり、兄と起居を共にせしこと極めて少なく、性質は同じからず、好尚(こうしょう)もまた相異れり。兄は謹慎にして、余は粗暴なり。兄は周到にして、余は粗笨(そほん)なり。兄は隠にして、余は頑なり。兄は敏にして、余は迂(う)なり。兄は数学を好めど、余は之を好まず。余は小説を好めど、兄は之を好まず。ただ酒を好むの癖相似たり。然(しか)れども兄は徐々(だんだん)小杯を傾くるを好み、余は一呼して巨盃を傾くるを好めり。囲碁を好むの癖、また相似たり。然れども兄は熟思精考、容易に子を下さず。余は手に堕(お)つて子を下し、敢えて思考を費やす。性質好尚(こうしょう)異なること、実に此の如きものあり。而(しこう)して兄が余を愛するの情は、言行(げんこう)の外に溢れり。兄余の一日も速(すみや)かに成業せんことを望む。故に昼夜、余に読書を勧めて措(お)かず。余があごを支え膝を搖(ゆる)がして苦吟するを見れば、兄は悦(よろこ)ばざりき。共に好(この)める酒も、祝祭の外(ほか)は共に飲みたることも少なく、たとえ之を共にするも、滑稽諧謔(こっけいかいぎゃく)、放歌激舞するに至らずして止みにき。碁も一回だに、共に囲みたることなし。唯々他人を標準として見れば、ほぼ相匹敵せるを知りしのみ。
嗚呼(ああ)生(は)や唯々教えを受く。而(しこう)して共に快楽をつくしたることなかりき。死やむなしく献之(けんし)の志を慕う。而(しこう)して年を減じて死に代うること能わざりき。兄実に余を子視せり。余もまた兄を親視せり。余を生みし者は父母なり、余をして人とならしめしものは兄たらずんばあらざるなり。
兄や余をして高等の学問を修めしめんとしたれど、鴑駘(どたい)竟(きょう)に千里に堪えず。学問文章旧面目を改むるものなく、呉下(ごか)の旧阿蒙(あもう)、江湖(こうこ)の窮措大(きゅうそだい)にして止まんとす。天資(てんし)のいたす所また如何ともするなし。ことに学未だ成らずして、からだ早く己に衰えぬ。われもと壮健、脚ことに強く、日に三十里も行くも未だ疲るるを覚えず、斗酒(としゅ)一呼(いっこ)して傾けしが、今はまた斯(か)かる勢(いきおい)なし。むかしは角力(かくりょく)をなし、競争をなすも、敢(あ)えて人にもゆずらざりしが、今は井戸の水を汲むだにものうく、常に門をとざして書を読むよりまた他の楽しみなし。半夜胸いたみ、気うえうるの時、世道(せどう)の日々に微なるをなげき、吾が生のゆくゆく休せるを思えば、われまた一滴の涙なき能(あた)わず。思うにわれ世にあることまた久しからじ。明日われ泉下(せんか)の土とならば、人間誰かまた我を弔わん。一死われ固(もと)より辞せずといえども、北堂(ほくどう)人あり、われ死なば侍養(じよう)の人を欠かん。苦しき浮世にもさすがにわれと覊(たずな)累をたつこと能(あた)わず。げにや親の恩は子を持って知り、骨肉の親しきは世を閲(け)みして知る。風樹(ふうじゅ)恨みあり、兄去ってまた起(た)たず。已(や)んぬるかな。呉宮人逝きて、西江空しく月をあまし、子期死して伯牙また琴を奏でず。かげろうを天地に寄す、真か仮か。今日弔い、明日弔わる。夢中夢あり、天道の是非また問わざるべし。さるにても冷やかなる浮世をよそにして静かに苔の下に眠る兄の身上うらやましさよ。 (明治二十九年) |
<参考> 青色文字について
劉怜・・三国時代魏・西晋の文人
隻影・・唯一つの物の影
心事・・心のなかで思うこと
煢々・・孤独なさま
零丁・・落ちぶれて孤独なこと
手澤・・身近において愛用したもの
皇城 =皇居
哭す =慟哭
流寓・・放浪して異郷に住むこと
好尚・・好み
迂・・にぶい
謹慎・・言動をひかえめにするすること
粗笨 =粗雑
隠・・内情が見えないようにする
子・・囲碁では碁石を数える時、子と表す
成業(せいぎょう、または、じょうごう)・・学業、事業を成し遂げること
勧めて措かず・・勧めた
諧謔・・冗談
献之・・中国の書家で王献之
鴑駘・・のろい馬、転じて、才能が劣ること
竟・・おわる、ついに
呉下の阿蒙
以前のとおり全く進歩のない者、また、学問のない者をいう。
阿は親しみをこめた語。中国の呉の魯粛(ろしゅく)が呂蒙(りょもう)に会って、談義した時呂蒙のことを武略に長じただけの人物と思っていたが、今は学問も上達し、かつて呉にいた時の君でないと言ったという故事からのことば。
江湖・・世の中、世間
窮措大・・貧乏な学者や書生
天資・・天性・うまれつきの資質
斗酒・・一斗の酒、大量の酒
角力・・相撲・力比べ
ものうい・・苦しい、つらい
半夜・・真夜中
世道・・社会道徳とそれを守る人の心
泉下・・あの世、死後の世界
北堂・・母
侍養・・身辺にいて世話すること
閲みする・・年月を過ごす、よくみる
已(や)んぬるかな・・今となってはどうしようもない
風樹(ふうじゅ)
樹は、静止していたいけれども、風が吹いて揺れざるをえない。子は親孝行をしたいけれども、親の命は待ってくれない。どうすることもできない嘆き。ここでは、親は兄のこと。
子期死して伯牙また琴を奏でず
伯牙(はくが)は自分の奏でる琴の音を理解してくれた子期(しき)を唯一の友としたが、その友の死後には弦を絶ち切り二度と事をひくことはなかったという故事 |
|