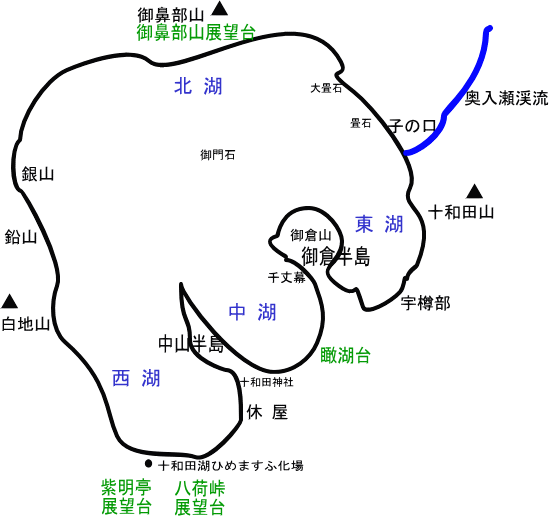十和田湖 夏 |
十和田湖を一周して夏の十和田湖を観ましょう
|
うたるべ
宇 樽 部
標高 400ⅿ
宇樽部からみた御倉半島です。約1100年前の十和田湖の大噴火で御倉山ができました。
|

|
かんこだい
瞰 湖 台
標高 583ⅿ
右は御倉半島の先端です。
十和田湖の最深部中海(なかのうみ)を見下ろすことができます。最大水深は327ⅿ、十和田湖の深さは日本3位です。1位は田沢湖(423ⅿ)、2位は支笏湖(360ⅿ)です。 |

|
やすみや
休 屋
標高 407ⅿ
雨上がりの十和田湖です。
|

|
わいない
和 井 内
標高 409ⅿ
住所は秋田県小坂町。
かつては魚の住まない湖でしたが、先人たちの努力によってヒメマスがすむ湖となりました。ここには十和田湖ひめますふ化場があります。 |

|
はっかとうげてんぼうだい
発荷峠展望台
標高 631ⅿ
湖に見えている半島は中山半島、正面には御鼻部山や八甲田連峰を望むことができます。 |

|
しめいていてんぼうだい
紫明亭展望台
標高 630ⅿ
手前は中山半島、奥は御倉半島。十和田湖の一部がハート形に見えます。
1927年(昭和2年)日本八景 湖沼部門1位になったことを記念した碑が近くにあります。
|

|
おはなべやま てんぼうだい
御鼻部山展望台
標高 1,011ⅿ
十和田湖はカルデラ湖であることが確認できる展望台です。
桂月は初回訪問時、十和田湖を展望する場所に御鼻部山を選びました。その日は小雨でしたが御鼻部山を選んで間違いでなかったと著しています。
|

|
ねのくち
子ノ口(または子の口)
標高 477ⅿ
ここは、奥入瀬川のスタート地です。約1万5千年前に大決壊して十和田湖の水が流れ出し奥入瀬渓流ができました。 |
 |
雲の上空をしたせる湖の水に心もすみわたるかな 桂 月
※したす・・・樹木などの陰で涼むこと
諸共に水にうつりて天地は月と我との外なかりけり 桂月
標高1,034ⅿの白地山(桂月は「しらじやま」と詠んでいます)からの眺めに満足した桂月が詠んだ歌は
かばかりのながめとたれもしらじ山世にすぐれたる処なりけり 桂 月
|